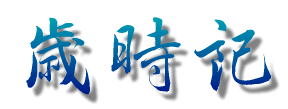
祭 1 96句 |
|||
|
作品 |
作者 |
掲載誌 |
掲載年月 |
| 席入の祭浴衣も京なれや | 山田弘子 | 春節 | 199503 |
| 祭着の吹かれ掛かれる家舟かな | 山田弘子 | 春節 | 199503 |
| 復興の町に景気の祭山車 | 稲畑汀子 | ホトトギス | 199805 |
| 海に顔向けて祭の中にゐる | 小澤克己 | 遠嶺 | 199808 |
| 祭笛躰ぬちに癌を養ひて | 城孝子 | 火星 | 199808 |
| 退職の教師が挑む祭笛 | 木村公子 | 沖 | 199808 |
| 祭団扇もつとも高き樹に凭す | 杉浦典子 | 火星 | 199810 |
| 鼻白粉引く間も誘ふ祭笛 | 南出律子 | 沖 | 199810 |
| 宵乗祭暁ヶを篠つく梅雨豪雨 | 松崎鉄之介 | 濱 | 199810 |
| 舟板を蹴る三番叟天満祭 | 品川鈴子 | ぐろっけ | 199810 |
| 橋くぐる天満祭の俳諧舟 | 品川鈴子 | ぐろっけ | 199810 |
| すと立てし小指美し祭笛 | 八木愁一郎 | ぐろっけ | 199810 |
| 子が手綱引いてやさしき祭馬 | 野沢しの武 | 風土 | 199811 |
| 鳥の木に風の集まる昇天祭 | 折原あきの | 船団 | 199811 |
| 荒きほど神意に適ひ喧嘩祭 | 竹野梢星 | 狩 | 199812 |
| すぐわかる祭帰りの五六人 | 久崎富美子 | 朝 | 199901 |
| 夕立だデートだ祭りだ不本意だ | 朝倉晴美 | 船団 | 199902 |
| 星出づる祭を明日の花街に | 宮津昭彦 | 濱 | 199903 |
| 祭髪結ひべらんめえ口調かな | 稲畑廣太郎 | ホトトギス | 199905 |
| きらきらと祭の列のそれつきり | 深澤鱶 | ヒッポ千番地 | 199905 |
| 検非違使の馬の暴れし賀茂祭 | 大山文子 | 火星 | 199906 |
| 祭の日青竹伐りの役もらふ | 能村研三 | 沖 | 199907 |
| 父在りてありて祭の笛高し | 小澤克己 | 遠嶺 | 199907 |
| ワッショイにソイヤと掛け声三社祭 | 橋本みず枝 | 澪 | 199907 |
| ちゃんちゃん祭子が草笛を吹きて待つ | 三輪温子 | 雨月 | 199907 |
| 祭風吐かせ提灯仕舞ひけり | 金國久子 | 青葉潮 | 199907 |
| 屋号しか知らぬ担ぎ手夏祭 | 大森慶子 | 沖 | 199908 |
| 星々のあはひに透けて祭笛 | 小澤克己 | 遠嶺 | 199908 |
| 祭馬稚児あらあらと乗せいたる | 山田弘子 | 円虹 | 199908 |
| どぜう屋ののれんをくぐる祭髪 | 山田弘子 | 円虹 | 199908 |
| 風に乗り祭囃子の海へ出る | 長山あや | 円虹 | 199908 |
| 自治会の祭りの水運ばさる | 山田六甲 | 六花 | 199908 |
| 夏の月遠く近くに祭り笛 | 久保田一豊 | いろり | 199909 |
| 風はいま路地の巾なる祭笛 | 土田栄 | 朝 | 199909 |
| 捨椅子にひるがほ絡む祭町 | 野路斉子 | 朝 | 199909 |
| 不在者のおほぜいが過ぎ祭過ぎ | 林朋子 | 船団 | 199909 |
| 磴焦がす大松明や那智祭 | 愛須真青 | 馬醉木 | 199910 |
| 人波にもまれ祭の顔となる | 稲垣松露 | 狩 | 199910 |
| 手拍子に神田祭の夜を締むる | 大久保白村 | ホトトギス | 199910 |
| 束髪のはらりと祭終はりけり | 小澤克己 | 遠嶺 | 199910 |
| 赤松の背高のつぽ祭来る | 奥田節子 | 火星 | 199910 |
| 夏芝居兄弟で舞ふ三社祭 | 金子八重子 | 酸漿 | 199910 |
| 祭笛句座のしじまに割込めり | 林翔 | 沖 | 199910 |
| 城灼けて天に鉾立つ祭舟 | 渡邊牢晴 | 雨月 | 199910 |
| 早苗田を渡りてきたる祭笛 | 鈴木夢亭 | 塩屋崎 | 199910 |
| 会へばまた友情育ち祭笛 | 嶋田摩耶子 | ホトトギス | 199911 |
| 夏祭日照雨一過に始まりぬ | 増田富子 | 馬醉木 | 199911 |
| 海鳴に棕櫚の葉さわぐ夏祭 | 原静寿 | 酸漿 | 199911 |
| きのふとは吹き手のちがふ祭笛 | 川島真砂夫 | 沖 | 199911 |
| 水銀柱ぐいぐい上がり祭来る | 白井剛夫 | 沖 | 199911 |
| 夜の奥へ打ち込む祭太鼓かな | 小松志づ子 | 沖 | 199911 |
| 旅に出て祭り踊りにとびこめり | 木部老正盛 | 澪 | 199911 |
| このあたり祭の庭と供物置く | 坂井まさき | 六花 | 199911 |
| はるかなる祭囃子に腰浮けり | 能村登四郎 | 芒種 | 199911 |
| 何となく祭近づく町の色 | 能村登四郎 | 芒種 | 199911 |
| 夏の川祭りのあとの足浸す | 小枝恵美子 | ポケット | 199911 |
| 母看ての帰り祭の灯に紛る | 前田一生 | 狩 | 199912 |
| 御霊ゆゑ降るは覚悟の祭とや | 三村純也 | ホトトギス | 199912 |
| 水飛沫木場の祭の山車がゆく | 小黒カツ | 酸漿 | 199912 |
| 長老や祭終りの衿はだけ | 小黒カツ | 酸漿 | 199912 |
| 雨あとの竹のさはだつ祭町 | 高橋さえ子 | 朝 | 199912 |
| 雨もまた祭の色として参加 | 稲畑廣太郎 | 廣太郎句集 | 199912 |
| なにし負ふ天神祭のうだりやう | 三嶋八千穂 | ぐろっけ | 199912 |
| 祭帯迷はずに選る鮫小紋 | 湯橋喜美 | 沖 | 200001 |
| 提灯のくらき貴船の宵祭 | 中村七三郎 | 七三郎句集 | 200001 |
| 乾く綿菓子祭のあとの虚しさは | 富田美和 | 澪 | 200001 |
| ちゃんちゃん祭昔の刻の流れゐる | 萩谷幸子 | 雨月 | 200001 |
| ネクタイを締めて祭の役果す | 平田安生 | 風土 | 200001 |
| 田の神を飾り巫子舞ふ収穫祭 | 関戸文子 | 酸漿 | 200002 |
| 曲稚児の仕草可愛ゆし祭獅子 | 田中としを | 雨月 | 200002 |
| みちのく訛とび交ひ祭は最高潮 | 山田をがたま | 京鹿子 | 200002 |
| 夜祭のわが門前の草魚売 | 田中藤穂 | 水瓶座 | 200002 |
| 海ほほづき売る店小さし祭の夜 | 田中藤穂 | 水瓶座 | 200002 |
| 浅草の街ごと酔って祭かな | 田中藤穂 | 水瓶座 | 200002 |
| 階段の埃祭りの朝静か | 星野早苗 | 空のさえずる | 200002 |
| 長閑なり朝に夕べに神祭る | 藤和子 | 円虹 | 200004 |
| 義士祭大阪にてもありにけり | 松崎鉄之介 | 濱 | 200004 |
| 百人町いまは祭の山車も来ず | 鷹羽狩行 | 狩 | 200005 |
| いつまでも帰らず父の祭客 | 鷹羽狩行 | 狩 | 200005 |
| 提灯を伸ばせば神田祭かな | 稲畑汀子 | ホトトギス | 200005 |
| 提灯に会場神田祭気分 | 稲畑廣太郎 | ホトトギス | 200005 |
| 暗がりに酔えるも県祭かな | 岸風三樓 | 朝 | 200006 |
| 祭の森百姓の兄匂ふなり | 島津亮 | 海程 | 200006 |
| おしきせの祭法被は身幅詰め | 品川鈴子 | ぐろっけ | 200006 |
| 機上より天神祭見ゆる帰路 | 稲畑汀子 | ホトトギス | 200007 |
| 血行の肩によどみし祭あと | 大牧広 | 沖 | 200007 |
| じゃらじゃらと急く手古舞に祭笛 | 當麻幸子 | 俳句通信 | 200007 |
| 手隠しに恥らひみせて祭菓子 | 平子公一 | 馬醉木 | 200008 |
| 祭来る神馬細身に磨きあげ | 内田雅子 | 馬醉木 | 200008 |
| 三社祭にゐるはづもなき樋口奈津 | 高橋邦夫 | 風土 | 200008 |
| パレードの馬具干されたる祭かな | 高橋花仙 | 風土 | 200008 |
| 街中の祭ちやうちん蛙出づ | 黒田咲子 | 槐 | 200008 |
| 照り降りの中を集めし祭寄付 | 能村研三 | 沖 | 200008 |
| 氏神に格差ありけり山王祭 | 藤井晴子 | 沖 | 200008 |
| 三社祭り終りしあとに参りけり | 久保田一豊 | いろり | 200008 |
| 歌口へ寄する唇知る祭笛 | 渡辺純 | 京鹿子 | 200008 |
| 祭 →2 | |||
2021年5月14日 作成