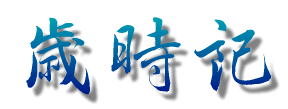
棗の実 103句
|
|||
|
作品 |
作者 |
掲載誌 |
掲載年月 |
| 青棗飾肘木の飛騨の家 | 松崎鉄之介 | 濱 | 199809 |
| 石窟へ道ひえびえと棗の実 | 皆川盤水 | 春耕 | 199811 |
| 棗の実裏木戸きいと鳴るばかり | 八木愁一郎 | ぐろっけ | 199902 |
| 王と並ぶ管仲の墓棗の芽 | 松崎鉄之介 | 濱 | 199906 |
| 棗落つ母の屋いまも棗落つ | 平橋昌子 | 槐 | 200001 |
| どこまでも空の深さよ棗の実 | 阿部悦子 | 酸漿 | 200002 |
| 椋鳥に半端な色の棗の実 | 櫻井多恵 | 朝 | 200002 |
| 旧邸の庭に一樹の青棗 | 有山光子 | 遠嶺 | 200101 |
| 地蔵盆青き棗に湖ながれ | 岡井省二 | 槐 | 200104 |
| 口誦をうながす碑なれ青棗 | 能村研三 | 沖 | 200110 |
| 一本の千代女の色に棗の実 | 神蔵器 | 風土 | 200110 |
| 噛んでゐて棗は甘くなりにけり | 岡井省二 | 槐 | 200111 |
| 棗の実一粒を染め敗戦日 | 倭文ヒサ子 | 酸漿 | 200112 |
| 棗の実飛騨の小雨は傘いらず | 榎本愛子 | 海程 | 200112 |
| 棗の実あまた熟れゐて誰もゐず | 木村真魚奈 | 京鹿子 | 200202 |
| 落葉して棗は人を拒むごと | 小澤スミエ | 狩 | 200203 |
| 夕晴れて二百十日の棗の実 | 山尾玉藻 | 火星 | 200210 |
| 郷愁の如き渋味の棗噛む | 中川芳子 | 濱 | 200210 |
| 棗の実美術館いま門を閉づ | 梅谷昌弘 | 雲の峰 | 200210 |
| 船津屋の灯にてらされて棗の実 | 内藤順子 | 酸漿 | 200212 |
| アンデスの歌声流る棗売 | 吉村玲子 | 円虹 | 200212 |
| さくと噛む棗の香りうすみどり | 吉村玲子 | 円虹 | 200212 |
| 棗の実夫少年の日を語る | 大山妙子 | 酸漿 | 200212 |
| 棗の実昼の教会点りをり | 影山わこ | 百鳥 | 200301 |
| 棗の実ぽろぽろ落ちてゐて廃家 | 城戸愛子 | 酸漿 | 200301 |
| 棗の実見頃ですよと文にかな | 百田早苗 | 六花 | 200301 |
| なつかしきあの娘はだあれ棗の実 | 中谷喜美子 | 六花 | 200310 |
| 伸び放題で風にあふらる青棗 | 府川みよ子 | 濱 | 200311 |
| 舟津屋の門にしだるる棗の実 | 辰巳陽子 | 雲の峰 | 200312 |
| 乃木旧居ひとつ灯れり棗の実 | 笠井育子 | 濱 | 200401 |
| シスターの笑顔すぎゆく棗の実 | 近藤きくえ | 槐 | 200401 |
| かの家の消えねば棗咲き居らむ | 井上信子 | 鴫 | 200410 |
| 乃木邸に駿馬ありし日棗の実 | 秋田谷明美 | 帆船 | 200411 |
| 棗生る青さ門辺の隣りあふ | 永田二三子 | 酸漿 | 200412 |
| 棗の実少女の拒否はガラス張り | 東亜美 | あを | 200412 |
| 棗くれし伯母もそを煮し母も亡し | 大橋敦子 | 雨月 | 200412 |
| それはさう棗とちがふ生なつめ | 戸田和子 | 鴫 | 200501 |
| 白川の砂にまぎれし棗の実 | 近藤きくえ | 槐 | 200501 |
| 忌日くる枝の先まで青棗 | 野澤あき | 火星 | 200511 |
| 嫁の来てはじめて棗の実を乾せり | 村上一葉子 | 濱 | 200512 |
| 般若心経唱う棗の実の青し | 竹内悦子 | 槐 | 200601 |
| 雨こぼす雲を真上に棗の実 | 糸井芳子 | 朝 | 200601 |
| 青空に先生を待つ棗の実 | 斎藤くめお | 対岸 | 200602 |
| 誰袖棚赤絵水指夜桜棗 | 東亜未 | あを | 200606 |
| 春愁や断食月(ラマダン)の地の棗椰子 | 内山花葉 | 沖 | 200607 |
| 朽ち果てし隊商宿や青棗 | 大西裕 | 酸漿 | 200610 |
| たべごろの棗となりし飛鳥川 | 岩下芳子 | 槐 | 200612 |
| 棗の実いくども返す砂時計 | 津田礼乃 | 遠嶺 | 200612 |
| 初釜やこだわりの朱の平棗 | 藤田宣子 | ぐろっけ | 200702 |
| 校庭に翁の像と棗の実 | 三崎由紀子 | 遠嶺 | 200702 |
| 細やかな若葉の中に棗咲く | 大山妙子 | 酸漿 | 200709 |
| 乃木邸の厩傷めり咲く棗 | 網野茂子 | 酸漿 | 200710 |
| 棗の実ひとり住まひの庭にあり | 岡和絵 | 火星 | 200712 |
| 棗の実賛美歌にふと耳を貸し | 菊池由惠 | 酸漿 | 200712 |
| 豊な日たわわに熟るる棗かな | 上藤八重子 | 酸漿 | 200712 |
| 権現の絵馬のうすれし棗の実 | 竹内弘子 | あを | 200801 |
| 零れ敷き羊の糞めく棗の実 | 藤平タネ子 | 濱 | 200802 |
| ふるさとの廊下のきしみ青棗 | 大鋸颯人 | 炎環 | 200810 |
| 棗の実こぼれて室の八嶋かな | 中島陽華 | 槐 | 200811 |
| 少年の日の夫にあり棗の実 | 長田曄子 | 火星 | 200812 |
| 棗降りなつめ忘れし空のあり | 長田曄子 | 火星 | 200812 |
| 砂棗噛めば旱のにほひかな | 原田達夫 | 鴫 | 200901 |
| 砂灼けて胡楊紅楊砂棗 | 原田達夫 | 鴫 | 200901 |
| 大山祇祀る棗の熟るる丘 | 大坪景章 | 万象 | 200902 |
| 棗の実こぼれて甘しセピア色 | 斉藤敬子 | 火星 | 200904 |
| 片頬の紅づく棗朝のキス | 品川鈴子 | ぐろっけ | 200909 |
| 掌は水汲むかたち棗受く | 北島和奘 | 風土 | 200912 |
| 古都風情残す曲阜の棗売り | 伊地知冶江子 | 苑 | 201001 |
| 希典の殉死悼むや棗の実 | 奈辺慶子 | 雨月 | 201001 |
| 棗熟れ通船堀の差配邸 | 田中きよ子 | 酸漿 | 201001 |
| 里古りてみる人なしに棗の実 | 川村欽子 | 雨月 | 201002 |
| ひさびさのひとり旅なり青棗 | 伊勢きみこ | 火星 | 201011 |
| 乃木大将も旅順も昔棗食ぶ | 上田明子 | 雨月 | 201012 |
| 棗の実葬内々に済ませしと | 田中藤穂 | あを柳 | 201012 |
| きのふ逝きし友より手紙棗の実 | 浅田光代 | 風土 | 201101 |
| ふるさとの片雲にあり青棗 | 小泉和代 | 酸漿 | 201101 |
| ポケットに棗をひとつ散歩道 | 年森恭子 | ぐろっけ | 201101 |
| 棗の香にふくらんでゐる紙袋 | 加藤みき | 槐 | 201102 |
| 吹き降りのあとつやつやと棗の実 | 竹内弘子 | あを | 201103 |
| 棗の実熟せども取る人の無き | 小林美登里 | かさね | 201301 |
| 棗の実音無く落ちて土の色 | 須賀敏子 | あを | 201301 |
| 目利から貰ひし棗初点前 | 山田六甲 | 六花 | 201301 |
| 実棗に十歩寄り道して帰る | 陽山道子 | おーい雲 | 201304 |
| 南国の終着駅の棗の実 | 陽山道子 | おーい雲 | 201304 |
| 欣一忌綾子の棗供へけり | 原田しずえ | 万象 | 201401 |
| 柚子棗南天の実を師に捧ぐ | 大坪景章 | 万象 | 201401 |
| 黒々と雨粒ふくむ棗の実 | 廣畑育子 | 六花 | 201403 |
| 棗煮る母の秘伝をそのままに | 会田三和子 | 沖 | 201411 |
| 乃木神社の棗大樹や薄もみぢ | 山田愛子 | 璦 | 201412 |
| 棗食む栗鼠の母子の心地して | 川崎利子 | 璦 | 201412 |
| 中腹の蕎麦屋の庭に棗熟る | 赤座典子 | あを | 201501 |
| いつのまにか怒りをさまり棗の実 | 加藤みき | 槐 | 201512 |
| 青棗光返してをりにけり | 近藤紀子 | 槐 | 201512 |
| 棗噛み瞑れば見ゆるもの多し | 白神知恵子 | 春燈 | 201601 |
| 棗の実雑器ばかりの陶器市 | 青谷小枝 | やぶれ傘 | 201602 |
| 不図たまるポイントカード棗の実 | 奥田筆子 | 京鹿子 | 201612 |
| 熟れ棗落つるにまかせ風木舎 | 大坪景章 | 椿垣 | 201612 |
| 朝な朝な棗若葉を愛でにけり | 手島南天 | 万象 | 201708 |
| 青棗ひからせ路地の日の動く | 片桐紀美子 | 風土 | 201711 |
| 大和へと抜くる古道の青棗 | 夏生一暁 | 馬醉木 | 201712 |
| 棗の実句会の行く時帰る時 | 大日向幸江 | あを | 201812 |
| 棗の実万葉仮名の碑を打てる | 升田ヤス子 | 六花 | 201812 |
| 人形のべべは赤色棗の実 | 杉原ツタ子 | 槐 | 201912 |
2021年10月10日 作成